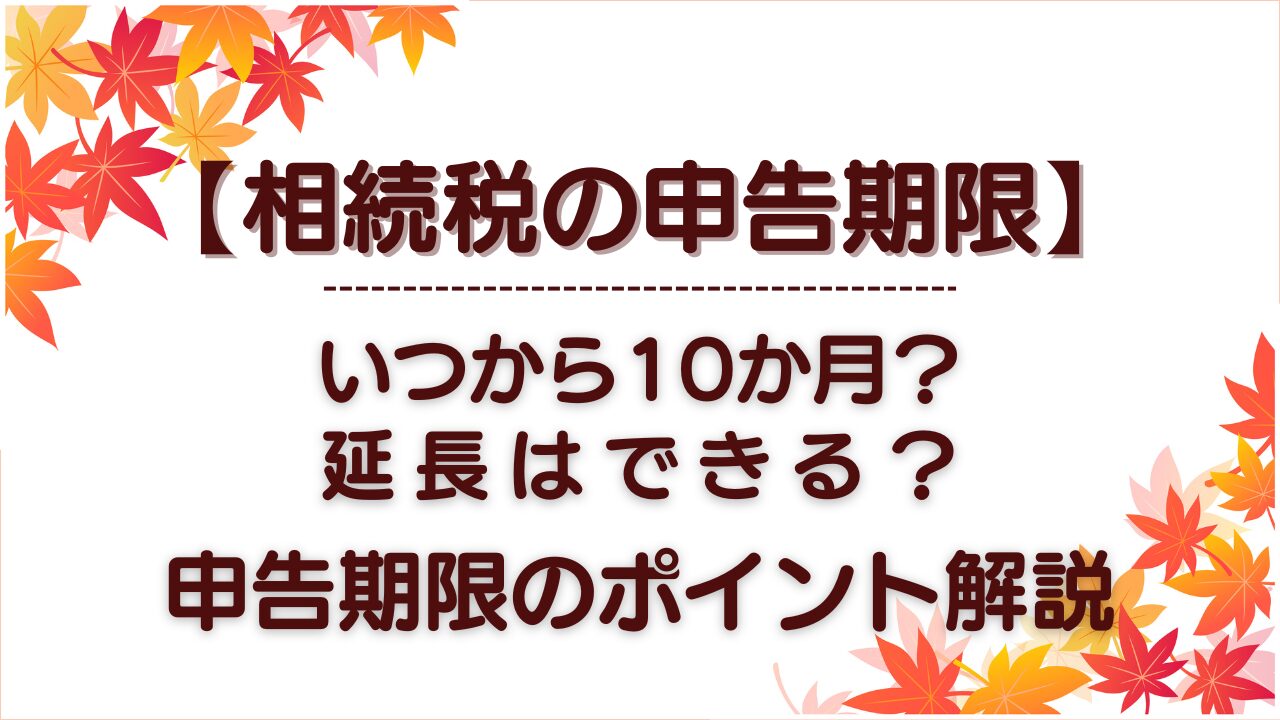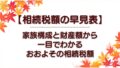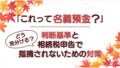🍁この記事のゴール🍁
- 相続税の申告期限がわかる!
→「いつから」10か月なのか
→期限は原則延長不可!過ぎてしまうと延滞税の可能性!
→期限を過ぎそうな場合は「未分割申告」をしよう!
この「10か月」を覚えておきましょう。
- いつから10か月なのか?(起算日は?)
- 期限内に申告できなかったらどうなるのか?
- 期限は延長できないのか?
と気になることもたくさんあると思います。
この記事で順番に解説していきますので、ぜひご参考くださいね!
相続税の申告期限は10か月!起算日について
申告の期限と方法
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。
例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。
続きを見ていきます。
申告の期限と方法
なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限とみなされます。
申告期限が土日祝だった場合は、いわゆる「翌営業日」が期限日ということになります!
【例外】通常の起算日「死亡日の翌日」に該当しないケース
前述のとおり、申告期限は「死亡を知った日(通常の場合は死亡日)の翌日から10か月」となりますが、この「死亡日の翌日」が起算日にならないケースもあります。
例えば、
- (被相続人の)失踪の宣告を受けて、死亡したとみなされた場合
- 胎児や幼児が相続人になる場合
- 遺言書によって財産を取得する場合(遺贈)
といった状況が該当します。
※一部抜粋ですので、詳しくは以下をご参照ください。
第27条《相続税の申告書》関係|国税庁
国税庁のページでは、それぞれ「どのような状況」が例外になり、「いつ」を起点とするのか定められていますので、特殊なケースの場合は確認するようにしましょう。
相続税を申告・納税する税務署
申告の期限と方法
相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地を所轄する税務署ではありません。
相続税の申告・納税する税務署は、被相続人の住所地にある税務署ということになります。
納税期限も同じく10か月!
項目「納税の期限と方法」を見てみましょう。
納税の期限と方法
相続税の納税は、上記の申告期限までに行うことになっています。
つまり、相続税を納付する期限は、申告期限と同じ10か月ということになります!
相続税の申告期限に間に合わなかったら?ペナルティについて
相続税の申告期限までに、
- 相続人と相続財産を確定させ
- 控除等を使って相続税額を計算し(相続税の申告書を作成し)
- 税務署に申告と納税
ここまで完了させる必要があります。
もし、10か月の期限に間に合わなかった場合はどうなるのかというと・・・
納税の期限と方法
申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。
そうなんです、申告期限を過ぎたりすると、相続税の他にペナルティの税が課せられることになるのです!
| 種類 | 内容 |
| 加算税 | ・故意に偽って申告したり(重加算税) ・故意ではないが申告しなかったり(無申告加算税) ・故意ではないが過小評価して申告したり(過少申告加算税) といったものがあります! |
| 延滞税 | 期限を過ぎた場合に発生するペナルティ! (期限日から超過した日数に応じてかかります) (税率は年によって変わります) |
期限を過ぎてしまった場合は、このうちの延滞税がかかることになります。
本来の納税すべき相続税に加えてさらに課税されてしまうため、相続税の申告・納付については、早めに準備するに越したことはありません!
【注意】
期限までに申告しても、納税が間に合わなかった場合も、利息にあたる延滞税がかかる場合があります!こちらもご注意ください。
申告期限を過ぎてしまった場合のデメリット
相続税には、基礎控除の他にも様々な控除や特例があり、うまく活用することで、相続税を抑えることができます。(それぞれ適用条件がありますので、必ず税理士に相談してくださいね!)
>これでわかる【相続税の基礎控除】計算式と注意したい法定相続人についても解説
そしてもし、期限内に相続税の申告ができなかった場合、
- 配偶者控除
- 小規模宅地等の特例
が使えなくなるデメリットがあることは、重要ですので覚えておきましょう!
それぞれ「配偶者が相続する場合」「土地を相続する場合」に影響しますので、該当する場合は特に注意しましょう。
※それぞれの控除・特例の詳細は、別途記事を準備中ですので、それまで国税庁のHPをご参照ください。
No.4158 配偶者の税額の軽減
No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
相続税の申告期限の延長は「原則不可」!
相続税の申告期限は、原則延長できません。
ただし災害等のやむを得ない事情がある場合は、特別に期限の延長が認められています。
例えば、新型コロナウイルスの感染が拡大していた時期においては、「災害による申告、納付等の期限延⻑申請書」を提出することで、個別対応として期限の延長が認められていました。
(参照:「災害による申告、納付等の期限延⻑申請書」の記載⽅法|国税庁)PDFが開きます。
直近でいうと、「令和6年能登半島地震」で被災された方向けに、期限の延長が発表されました。(参照:「令和6年能登半島地震」により被災された納税者の相続税及び贈与税に係る申告・納付等の期限の延長について)
このような非常時を除き、原則期限の延長はできませんので、期限順守で申告と納税をしましょう!
【よくある疑問】税務署から通知は来るのか?
相続税を申告・納税する相続人に対して、税務署から「相続税についてのお尋ね」といった通知が届くことがあります。
ですがこの通知は、被相続人の生前の所得水準や所有している不動産、支払った生命保険の内容等によるようで、相続税の申告義務がある人全員に対して送られるものではありません。
つまり、相続税の申告見込みのある人に対して、死亡から半年後くらいにこの「お尋ね」の通知が届く人もいれば、相続税の申告が必要であるにも関わらず、「お尋ね」の通知が届かない場合もあります。
ですので、「お尋ね」の通知に頼らず、相続税の申告が必要な方は、早めに動いて申告・納税をするようにしましょう。
「納付書」は自身で用意する!
ちなみに、相続税の申告をした後、税務署から納付書が送られてくると思われていることがありますが、そのようなことはありません!
申告後、納付書は自身で作成し、納付することになります。
(税理士に申告書の作成を依頼している場合は、税理士が用意してくれることもあります)
こちらも忘れないように準備し、期限内に納税まで完了させましょう。
期限内に申告するためのポイント
相続税の申告期限までに、速やかに申告の準備をすることが大切ですが、そうはいっても「遺産の分割方法で、相続人の間でもめていてなかなか決まらない!」といった状況はよく聞きます。
あとは「相続税がかからないと思っていたら、後から大きな財産が見つかって、相続税の申告が必要になった!」といったケースで、申告期限まで時間がないといったこともあり得ます。
そういった場合、どうしたらよいのか?というと「未分割でいったん申告をする」という方法があります!
いわゆる「未分割申告」ですが、ひとまず法定相続分で遺産を取得したものとして相続税を計算し、期限内に申告することです。
このとき、必ず「申告期限後3年以内の分割見込書」というものも一緒に提出しておきましょう。
これがなければ申告期限を過ぎてしまった場合のデメリットでご紹介した
- 配偶者控除
- 小規模宅地等の特例
が使えなくなるためです!
その後、無事に遺産分割協議がまとまり、もし申告内容と税額が異なる場合は
- 修正申告(当初の申告より税額が多くなる場合)
- 更正の請求(当初の申告よりも税額が少なくなる場合)※
をしましょう。
(※更正の請求ができるのは、分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内です!)
参照:No.4208 相続財産が分割されていないときの申告|国税庁
それとは別に「申告はしたけど、相続税を納付するための資金がない!」といった場合の対策については、別途記事を作成中ですので、もうしばらくお待ちください。
まとめ
ここまでお伝えしてきた相続税の申告期限について、おさらいしましょう!
まず、相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内です。
(例:1月6日に死亡した場合→その年の11月6日が申告期限)
相続税の納付期限も、申告期限と同日です。
申告・納税ともに、被相続人の住所地にある税務署にすることになります。
もし、申告期限までに申告できなかった場合は、延滞税がかかる可能性がありますので、早め早めに準備するよう心掛けましょう。
(※繰り返しになりますが、申告期限を過ぎてしまうと、配偶者控除や小規模宅地等の特例が使えなくなります!)
万が一、期限を過ぎそうな場合は
- 未分割で申告する(「申告期限後3年以内の分割見込書」も添付する)
- 税額が異なる場合は、必要に応じて修正申告または更正の請求をする
ようにしましょう。
相続税の申告は、必要書類を集めたり、専門的な計算が必要になったりします。
うまく税理士の力も借りながら、期限を厳守して申告しましょう!