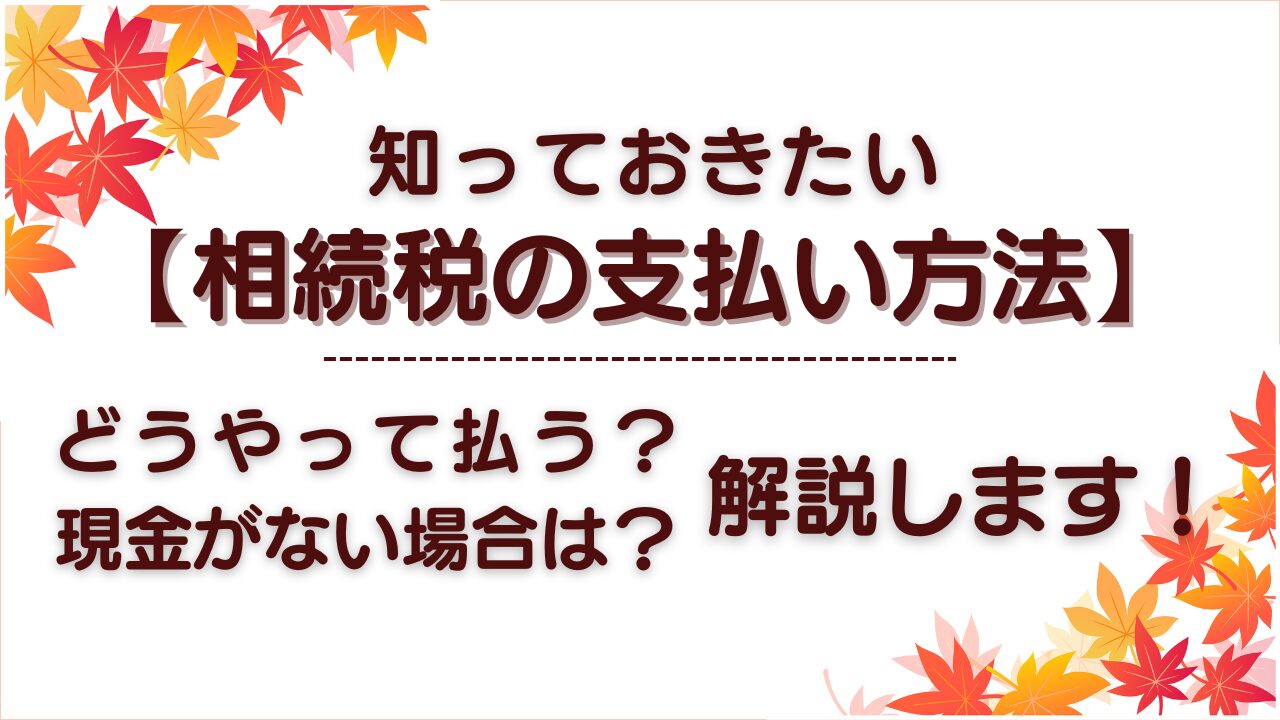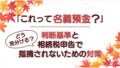🍁この記事のゴール🍁
- 相続税の支払い方法がわかる!
→具体的な4つの方法(コンビニでも、クレジットカードでもOK!)
→支払いは「原則現金一括」!
→「支払うのが難しそう…」そんなときに検討すべきこと
突然相続が発生して、しかも「相続税が発生する!」となると、多くの人が初めてで戸惑うことと思います。
相続税を支払うための【基礎知識】
詳しくはこちらをご参照ください。
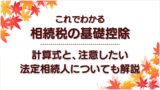
相続税は、相続において何かしらの財産を取得した人が支払うことになります。
- 相続によって財産を受け取った相続人
- 遺言書によって財産を受け取った人(受遺者)
- 相続時精算課税制度によって財産を受け取った人
が該当します。
反対に、以下の人は「相続財産を受け取っていない」ために、相続税の申告も納付も不要です。
- 家庭裁判所で相続放棄をした人(ただし、生命保険金を受け取った人は相続税がかかる可能性があります)
- 遺産分割協議において、一切の財産を相続しないと決まった人
■どこに支払うのか?
相続税の申告書の提出先と同じで、被相続人の死亡時における納税地を所轄する税務署となります!
相続税を支払う相続人(例えばあなた!)の納税地を管轄する税務署ではないため、要注意です。
■いつまでに支払うのか?
相続税の申告期限は10か月です!
詳しくはこちらをチェックしてくださいね。
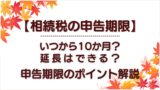
■どうやって支払うのか?
選択肢は4つあります!
①金融機関(銀行等)の窓口で支払う
②コンビニで支払う
③クレジットカードで支払う
④税務署の窓口で支払う
次の章で詳しく解説していきますね。
相続税を支払う(納付する)4つの方法
支払い方法について、順番に解説していきます。
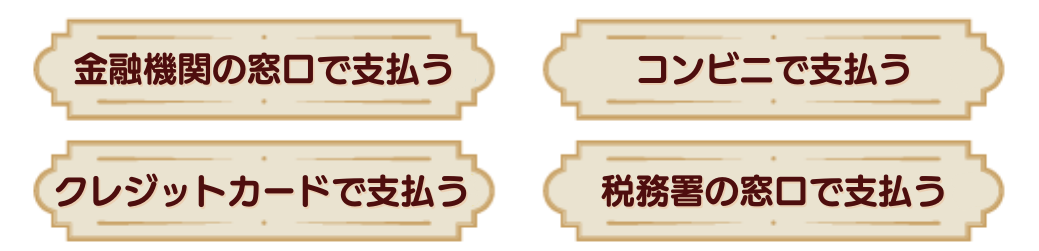
※【納付書について】
各項目にも記載していますが、相続税を支払う際の納付書は、税務署は用意してくれません。
自身で作成し、納付の際に一緒に提出するものになります。
(納税通知書のようなものを送られてきません!)
ですので、支払い方法ごとに「納付書はどうするのか」といった点にも注意しましょう。
金融機関(銀行等)の窓口で支払う
多くの人が選択している支払い方法です。
金融機関の窓口なら、納付書も備え付けでありますから安心です。
※納付書自体は、自身で書いて用意しましょう!
他に注意したいポイントがあります!
- 納付書の記入方法は、納付書の裏面を参照してください。また、住所、氏名、税額、申告書を提出した税務署名など、必要事項の記入漏れがないよう、ご注意ください。
- 金融機関や税務署の窓口では、クレジットカードによる納付はできません。
納付書の書き方に注意が必要なのと、窓口ではクレジットカードでは払えませんので現金を用意しましょう。
手数料はかかりませんので、その点はメリットです。
コンビニで支払う
他の税金について、コンビニで支払っているという人もいるかと思います。
それと同様に、相続税もコンビニで支払うことができます!
ただし、デメリットもありますので、あらかじめ把握したうえで利用しましょう。
まずは納付書についてです。
- 自宅のパソコン等で作成したQRコードを使用し、国税庁長官が指定した納付受託者(コンビニエンスストア)へ納付を委託することにより国税を納付する手続です。
どういうことかというと、つまりコンビニで支払う場合は、専用の「バーコード(納付書)」が必要になるため、それを事前に発行(出力)する必要があります。
手ぶらで窓口に行っても支払うことはできませんので、注意が必要です!
詳しくは国税庁のHP(G-2-6 コンビニ納付(QRコード))を参照ください。
(当記事もこのページから抜粋しています)
他に気を付けたいポイントは、以下の通りです。
- 30万円以下で利用が可能
- 領収書は発行されない(必要な場合は、他の方法で支払いましょう!)
- 実際の支払いは現金のみで、クレジットカードや電子マネーでの支払いは不可
クレジットカードで支払う
インターネットが使える環境であれば、クレジットカードで支払うのもひとつの手段です。
(支払額1,000万円までならOK!)
ですが、
納付税額に応じた決済手数料がかかります。
そのため、納税額が大きい場合は注意が必要です。
また、クレジットカードで払う場合も、領収書は発行されません。
「それなら、銀行窓口やコンビニでクレカで払おう!」と思っても、これらの手段でのクレジットカード決済は不可ですので、この点にも気を付けましょう!
税務署の窓口で支払う
相続税の支払いは、申告をする税務署と同じ税務署になりますので、提出の際に一緒に相続税の納付ができるのが、税務署の窓口で支払う一番のメリットです。
※ただし、金融機関窓口と同様、納付書自体は自身で書く必要があります!
また、先にも少しお伝えしたように、申告・納税先の税務署とは「被相続人の死亡時における納税地を所轄する税務署」のことです。
納税する人の近所の税務署ではありませんので、もし納付先の税務署が遠方にある場合は、もしかしたら違う方法での支払いを検討したほうがいいかもしれません。
支払いは「原則現金一括」で!
どの支払い方法を選択したとしても、相続税の支払いは、原則現金一括となります!
そして相続した財産額が大きければ大きいほど、納付する相続税額も大きくなります。
そこでもしかしたら、「現金が、足りない!払えそうにない!」という人もいるかもしれません。
(例:相続した財産が不動産ばかりの場合)
そのような場合にできることを紹介していきます。
まず現金化できるものは現金化する
「原則一括現金」での支払いですから、現金化できるものは売却等によって、なるべく現金を用意できるように努めましょう。
例)相続した財産(株式や信託など)を売却し、現金化する
または、自身がもともと保有しているものを売却して現金化する、など
実際、この後紹介する延納・物納といった国が認めている制度もありますが、活用するにはかなりハードルが高く、それゆえ実績も多くはありません。
そういったことからも、なるべく早めに、可能な限り現金化し、「現金で一括で支払う」ことができるように準備をしましょう。
※相続財産を売却し現金化する場合、相続手続きをしてからの売却になるため、早め早めの手続きがおすすめです!
※不動産の売却は、買い手がなかなか見つからない等により、換金に時間がかかる場合がありますので、「何を売却するか」も含めて、早めの検討が賢明です。
延納または物納を検討する
- 延納とは、何年かに分けて相続税を支払う方法
- 物納とは、相続などで取得した財産そのもので納める方法
のことです。それぞれ国税庁のHPから抜粋して説明していきます。
■延納について
相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦の方法(年払い)で納付することができます。
延納期間中は利子税の納付が必要となります。
つまり内容をまとめると、
- 相続税額が10万円以上である
- 現金一括納付をすることが難しい事由がある
- 延納税、利子税の額に相当する担保を提供できる
(※延納税額が100万円以下、延納期間が3年以下の場合は、担保の提供は不要) - 延納申請期限までに、延納申請に必要な書類を税務署に提出する
これらを満たしたときに、延納することができるということになります。
(ただし審査があります)
※ここでは概要のみをお伝えしています。担保として認められている種類や延納申請期限、延納機関や延納利子税については、国税庁HP|No.4211 相続税の延納をご参照ください。
■物納について
延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による納付(物納)ができます。
つまり、先の延納ですら困難な場合に限り、また申請期限までに必要書類一式を提出することで、相続財産によって物納することが認められています。(ただし審査があります)
問題は、何が物納として認められる相続財産なのか、ですね。
- 日本国内に所在する財産
- かつ、次の順位(1から5の順)によること
と規定されています。
<第1順位>
1 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
2 不動産および上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
<第2順位>
3 非上場株式等
4 非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
<第3順位>
5 動産
※物納の場合も、一定期間利子税がかかります。
※特に、証券や不動産は「不適格な財産」についても明記しており、また例外等もあります。詳細については国税庁HP|No.4214 相続税の物納を確認してください。
何はともあれ、困ったら早めに税理士に相談を!
「相続税が払えそうにない!」というときにできることを紹介してきましたが、困ったときは、迷わずにまずは税理士に相談しましょう!
特に、「相続税の申告」を扱っている税理士に頼ることをお勧めします。
相続は、相続人の人数や関係性、相続税額や財産状況など、それぞれ状況がまったく異なります。
支払う現金がないから「じゃあ延納で」と考えるのではなく、それぞれの状況に応じた最適解を、相続税全般を理解している税理士と一緒に探っていくのが一番かと思います。
また実際に、延納・物納が認められるケースは、全国的にもとても少ないです。
国税庁の発表によると、令和5年度に延納が許可された件数は864件(申請数は1,149件)でした。
そして、令和5年度の物納の許可件数は、わずか16件(申請数は23件)でした。
(参照:相続税の延納処理状況等、相続税の物納処理状況等)
延納、物納の申請をしたことがある税理士もおそらく少ないと考えられます。
そのため、こうした国の制度も視野に入れつつ、現実的に「どうやって支払うのがベストなのか」を、相続税に詳しい税理士に、早めに相談しましょう。
※税理士に相続税申告を依頼する場合は、税理士報酬が発生します。
相続した財産の0.5%~1.5%が相場ですが、HPで報酬額を公開しているところも多いため、気になる方事前に確認するようにしましょう。
まとめ
それでは、ここまで説明してきた相続税の支払いについておさらいしましょう!
【相続税を支払う方法】
■だれが?
→ 相続において何かしらの財産を取得した人が
■どこに?
→ 被相続人の死亡時における住所地を所轄する税務署に
■いつまでに?
→ 10か月以内に
■どうやって?
→ 原則現金一括で!
→ 次の4つの方法のいずれかで
①金融機関(銀行等)の窓口
②コンビニ
③クレジットカード
④税務署の窓口
もし、申告期限までに申告・納税ができなかった場合は、延滞税がかかります!!
期限の延長も原則不可ですので、申告だけでなく納税についても早めに考えておきましょう。
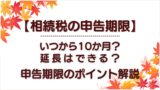
万が一、相続税を支払うための資金がないような場合は、
- まず現金化できるものは現金化する
- 延納または物納を検討する
ようにしましょう。
ですが、解決の一番の近道は、早々に税理士に相談することです!
お困りの際は、ぜひお気軽にご相談くださいね。